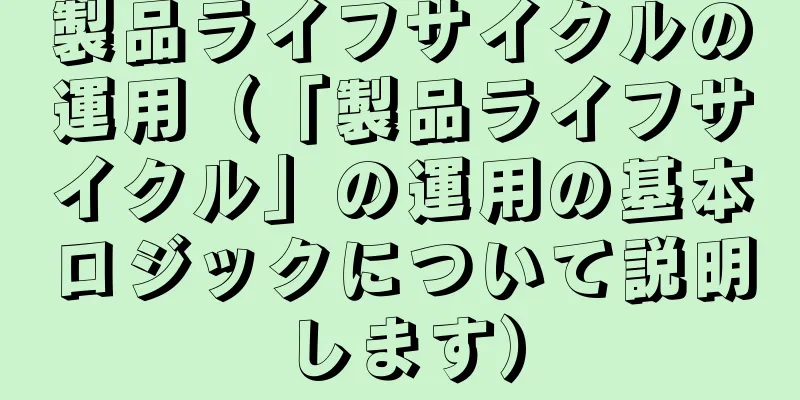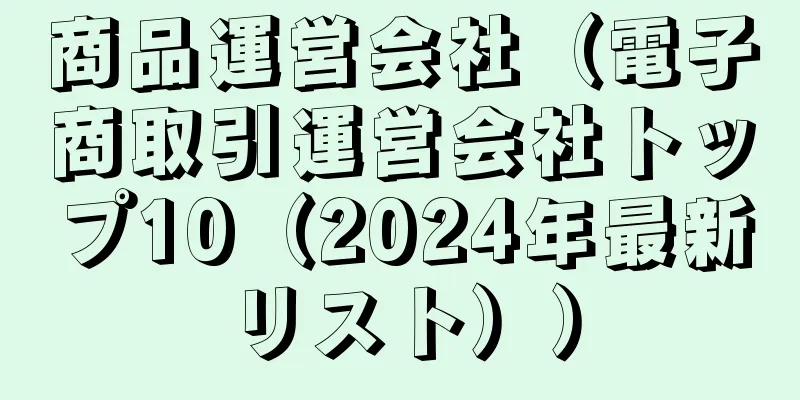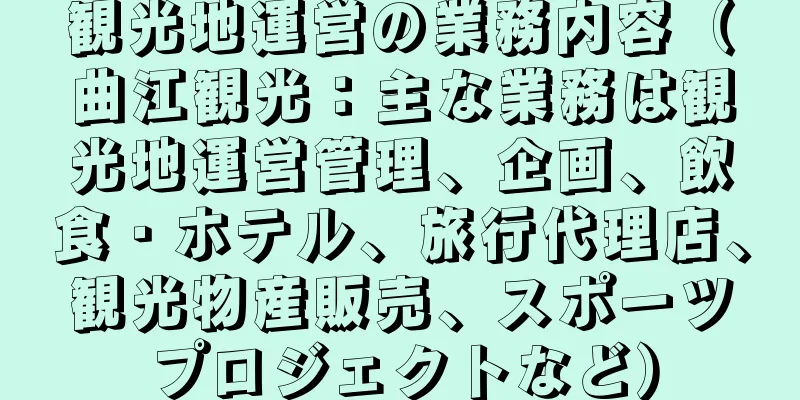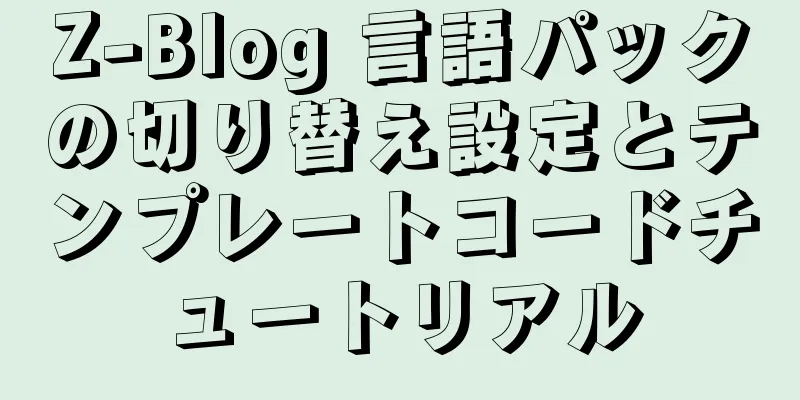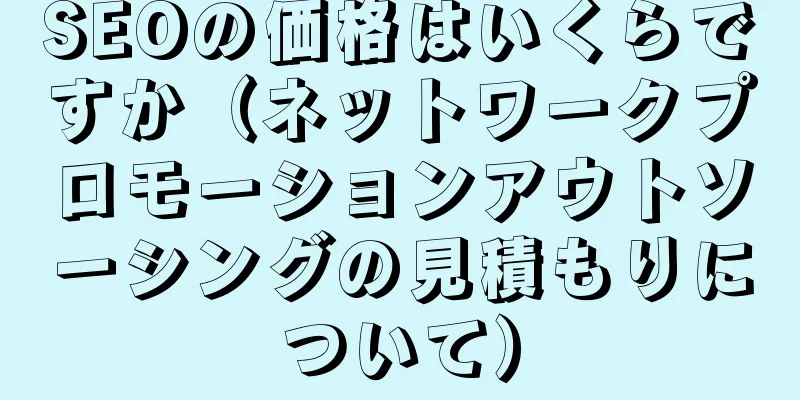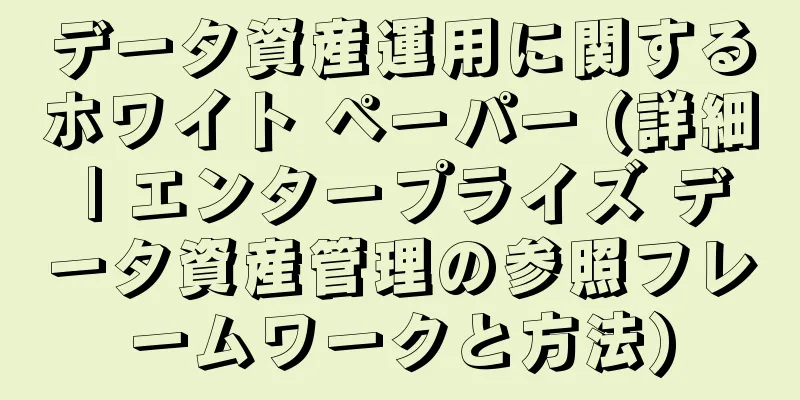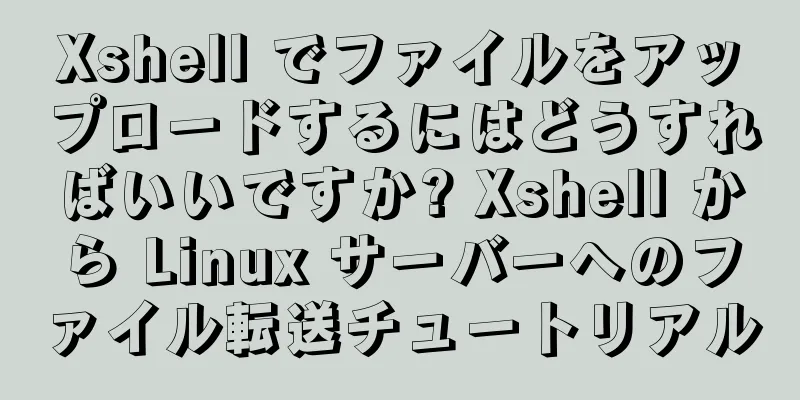基本的な業務内容(日本のコンビニエンスストアの進化)
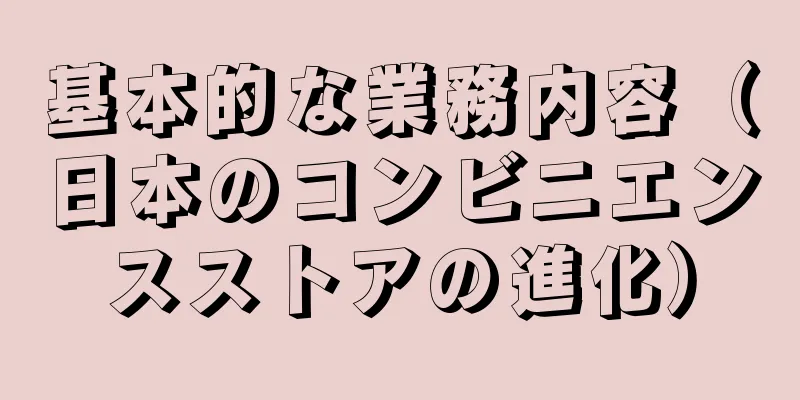
日本のコンビニエンスストアの進化出典:中国日本大使館 ほぼすべての国の日本旅行ガイドには、「コンビニエンスストアに行く」という推奨が含まれています。 「日本のコンビニで何を買うべきか」はソーシャルネットワーク上で永遠の話題となっている。 店の棚には、さまざまな種類の食品に加えて、洗濯用洗剤、傘、ストッキング、タオル、デンタルフロス、バンドエイド、消しゴム、風邪薬など、あらゆるものが並んでいます。深夜便で到着した観光客と、残業を終えて疲れて帰宅した労働者が同じ列のハイチェアに座り、電子レンジで温めた深夜のおやつを楽しみ、短い交流のあと、それぞれの目的地へと向かいます。 つまり、この店では販売方法から商品のパッケージに至るまで、すべてが「利便性」を重視しているのです。 現在、日本全国に約56,000店のコンビニエンスストアがありますが、少子高齢化の影響でその数は緩やかに増加しています。 日本の関連消費市場の調査統計によると、日本人の約80%が少なくとも週に1回はコンビニエンスストアを利用しており、回答者の半数以上が家を借りたり買ったりする際に、近くのコンビニエンスストアの密度や距離に基づいて生活の利便性を考慮するとのことです。 仕事が遅く終わることを心配する必要がありません。コンビニに行けば、忙しい一日の後に食事や缶ビールで空腹を満たすことができます。 1974年「コンビニ元年」 コンビニエンスストアは日本語で「コンビニ」と呼ばれ、英語のConvenience Storeの略語から派生した外来語です。 このビジネスモデルは米国発祥で、顧客の需要に基づいて、アイスショップ「サウスランド・アイス社」の従業員であるジョン・ジェファーソン・グリーンによって考案されました。当時、この店では主に氷を売っていました。夏場の氷の需要が高まる時期には、店舗の営業時間を「年中無休、週16時間営業」に変更し、より多くのお客さまの利便性を高めました。 ジョンは、顧客の要望に応えて、もともと氷だけを売っていた店に、パン、卵、牛乳といった日用品も加えました。これがコンビニエンスストア「セブンイレブン」の原型となった。 コンビニエンスストアのビジネスモデルは、経済が好況だった1966年頃に日本に導入されました。 当時、日本の都市化はますます進み、人々のライフスタイルは絶えず変化し、発展を求めて大都市に集まった若者たちが最小の家族単位となっていました。従来の「週末に家族で大型スーパーマーケットへ買い物に行く」という消費シーンは減少傾向にあった。仕事が終わった後、人々は料理をする気力もなく、お腹を満たすために手早く手軽に食べられる食べ物が新たな需要となりました。 こうした要望を踏まえ、1970年に日本能率協会はコンビニエンスストア研究会を設立し、日本人にとってより適したコンビニエンスストアのあり方を真剣に考え、開発し始めました。翌年、アメリカ各地に「コンビニエンスストア調査研究団」を派遣し、調査・研究を行い、1972年4月には「日本コンビニエンスストア発展会議」を開催した。同年、中小企業庁は「コンビニエンスストアガイド」を発行し、中小企業経営者に「フランチャイズチェーン方式」のコンビニエンスストアモデルを啓発的に紹介し始めました。 1973年11月、イトーヨーカ堂はサウスランドアイス社から関連認可を得て、ヨークセブン社を設立しました。翌年5月には東京都江東区豊洲に食品や酒類をメインに販売するセブンイレブン1号店をオープンした。当時、路面店での買い物に慣れていた日本人にとって、セブンイレブンの明るくシンプルな店内と、豊富で多様な陳列は生活に大きな利便性をもたらしました。 アメリカのJJローソンミルクカンパニーと提携したローソンや、日本のスーパーマーケットチェーン西友が設立したファミリーマートも、次々に第1号店をオープンした。 1974年は日本において「コンビニ元年」と呼ばれた。 バブル経済の時代に、日本のコンビニエンスストアは最初の爆発的な成長を経験し、時の試練を経て徐々に成熟し始めました。また、この時期は、一般消費者の視点から見ると、コンビニエンスストアがますます競争を激化させ、顧客を維持するためにあらゆる手段を講じていることに気づくでしょう。 例えば、今では日本のコンビニエンスストアでよく見かける新聞や雑誌は、かつてはローソンの特徴の一つでした。 1987年、セブンイレブンは、営業時間外に公共料金を支払いたい人が増えていることを察知し、店内でバーコードをスキャンして24時間支払いができる日本初の公共料金収納サービスを開始しました。 1991年3月からバブル経済が崩壊し、日本経済は深刻な衰退を経験しました。コンビニエンスストアはもはや昔ほど繁盛していない。地元の小規模なコンビニエンスストアの中には、大企業に買収されたり、経営不振により閉店したりしたところもあります。 この時期から2000年代初頭にかけて、日本のコンビニエンスストアの状況は徐々に明らかになり、ファミリーマート、ローソン、セブンイレブンの「ビッグスリー」が買収や合併を通じてますます強力になっていった。日本国内での展開だけでなく、フランチャイズモデルを活用してアジアの他の国や地域にも店舗を展開しました。 1992年、セブンイレブンは深センに5店舗をオープンしました。 1996年7月、ローソン初の中国本土店舗が上海の古北新区にオープンした。 日本には「ビッグスリー」以外にも、独自の特徴を持った中小規模のコンビニエンスストアや、地域性を重視したコンビニエンスストアが数多く存在し、それぞれが独自の顧客基盤を持っています。 例えば、北海道に多いセイコーマートは、北海道ならではの商品開発に力を入れており、道内の様々な村や町の農家と連携して地域限定商品を発売することも多いです。山崎実業株式会社が展開する「デイリーヤマザキ」はパンの有名ブランドで、多彩な焼き菓子が同店の大きな特徴となっている。 JRの駅構内でよく見かけるニューデイズは、実はJR東日本が経営するコンビニエンスストアで、主にJRの沿線駅に出店しています。 コンビニには隠れた世界がある 日本では、コンビニエンスストアをより「便利」にするために、さまざまな研究や改革が行われ、よりコストパフォーマンスの高い商品からサポートサービスまで、あらゆる面で改善・グレードアップする努力を惜しみませんでした。 今日、どのコンビニエンス ストアに行っても、店内の全商品の約 30% から 50% をプライベート ブランド製品が占めていることに気付くでしょう。これらの商品は長い間、コンビニエンスストアの戦場となってきました。コンビニエンスストアの加盟店がコストを保証できるだけでなく、消費者は高品質と低価格を享受できるようになります。 景気低迷のさなか、日本人も全般的に「消費のダウングレード」を始めた。 主婦は日用品を買うのに安いディスカウントストアに行くことを好み、若者はより高価で新しい日用品にお金を使うことを嫌がります。これまで頻繁に新商品を発売し、多様性を重視してきたコンビニエンスストアにとっては大きな打撃となることは間違いない。 ローソンとファミリーマートは「自らを救う」ため、手軽に食べられるパンやスナック菓子などの自社ブランド商品を発売した。その後数十年にわたり、有名ブランドとの提携もコンビニエンスストアで頻繁に採用される戦略となりました。 例えば、ローソンはかつて大阪王将餃子とコラボして、揚げ餃子味のフライドチキンナゲットを発売したことがあります。焼肉レストラン秀州園とコラボレーションした特製サラダを発売した。 その後数十年にわたり、有名ブランドとの提携はコンビニエンスストアで頻繁に採用される戦略となりました。例えば、ローソンはかつて大阪餃子と提携して、揚げ餃子味のフライドチキンナゲットを発売したことがあります。バーベキューレストランXuxuenと提携し、特製サラダを発売しました。 一部のコンビニエンスストアでは、宅配サービスや水道・電気料金の支払いに対応しており、ほとんどのコンビニエンスストアは主流のチケットシステムに接続されています。たとえば、球技や公演、ディズニーのチケットなどは店内の券売機で購入できます。一時コピー、プリント、FAX…これら全てがコンビニで一気に完了します。 印刷やATMなどの付加価値のないサービスを提供する商店は、コンビニエンスストアのスペースを使用するための機械の料金のみを支払う必要があります。消費者は利便性を得られ、企業は物件を個別に借りる費用を大幅に節約でき、まさに双方にメリットのある状況が実現しました。 コンビニエンスストアの社会的特性 コンビニエンスストアは長い間、日本社会の象徴でした。非常に便利なサービスや商品の販売を国民に提供するだけでなく、その数が多く密集していることから、日本社会に大きな雇用機会も提供しています。一般的に、日本のコンビニエンスストアは2交代制または3交代制を採用しており、仕事内容は比較的単純で固定的です。このような時間モデルと単純な仕事内容は、柔軟な就業ニーズを持つ多くの人々を引きつけ、仕事と勉強を両立する学生、家族の世話をする必要がある主婦、その他のフリーランサーなど、さまざまなグループの就業ニーズを満たしています。コンビニエンスストアの柔軟な勤務時間は、間違いなくこのグループの人々の主なアイデンティティ以外の時間の空白を埋めている。 コンビニエンスストアの離職率は他の職種に比べて高いものの、コンビニエンスストアの新入社員研修は、新入社員ができるだけ早く業務に慣れ、そのような離職率でも店舗の正常な運営やスタッフの離職に影響が及ばないようにするための大規模で効率的かつ迅速な方法となっています。基本的な職務内容研修に加え、コンビニエンスストアの特性(店舗数が多い、広範囲に展開している、24時間営業)を踏まえ、コンビニエンスストアスタッフに対する店内・店外の安全研修も重要な役割を果たしています。 一般的に、日本のコンビニエンスストアは2交代制または3交代制を採用しており、仕事に必要な教育要件は比較的低いです。 厚生労働省が2020年に発表した「外国人雇用状況調査」によると、2019年10月末時点で日本で働く外国人は約166万人で、前年比14%増加した。これらの人々が働く主な場所はコンビニエンスストアです。ローソンは、日本での留学や就労を希望する外国人が来日後すぐにコンビニエンスストアで働けるよう、ベトナムと韓国に関連研修機関を開設し、基礎的な就労スキルの研修を行っている。 前述の高齢化現象と深刻な労働力不足に伴い、白髪の高齢者の中には「補助的労働」としてコンビニエンスストアで働くことを選択する人もいるだろう。 今年5月13日、都筑警察署の下山幸夫署長はファミリーマート南山田3丁目店の従業員2人、西巻理恵さんと川崎奈々さんに感謝状を贈った。店内で働いているとき、年配の男性が電話をしながらATMを操作しようとしているのを目撃した。通信詐欺ではないかと心配した彼らはすぐに警察に通報し、高齢男性を金銭的損失から救った。これは、コンビニエンスストアの従業員が顧客の安全について細心の注意を払っており、コンビニエンスストアの安全教育が不可欠であることを示しています。 最近では、多くのコンビニエンスストアが24時間営業ではないものの、夜遅くまで営業しています。夜間に発生する可能性のある犯罪行為に対処するため、日本のコンビニエンスストアは、緊急事態や犯罪に遭遇した住民がタイムリーに店員に助けを求めることができるよう、2000 年代初頭から地元の警察署と連携してきました。 経済産業省の統計によると、2013年には日本国内のコンビニエンスストア6,914店が女性からの緊急要請を8,641件受け、2,893店が子どもからの要請を3,641件受け、9,342店が高齢者や認知症患者への介護サービスを12,645件提供した。 命を救うコンビニエンスストア 日本は自然災害が発生しやすい国です。コンビニエンスストアは、昔から災害救援システムにおいて極めて重要な役割を果たしてきました。 1995年1月17日の阪神淡路大震災後、セブンイレブンは被災地に店舗を構えていなかったにもかかわらず、ヘリコプターやバイクを使って救援物資を輸送するなど全力を尽くした。当時関西に本社があったローソンも大きな被害を受けたが、被災地の店舗に物資を供給するためヘリコプターを派遣した。こうした行動により、多くの命が救われ、小さなコンビニエンスストアにもっと注目する人が増えました。 2005年、日本の関東地方の8都府県市(東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、横浜市、千葉市、川崎市、さいたま市)は、コンビニエンスストアグループ9社や吉野家、モスバーガーなどの一般飲食店と協定を結び、災害発生時に営業を可能な限り維持しながら、帰宅困難者に対して飲料水、トイレ、地図など基本的な支援を提供することになった。 この活動に参加する店舗は、困っている人々にタイムリーな緊急援助を提供できるよう、目を引くステッカーを店の入り口に掲示します。その後、協定は38都道府県と9政令市に拡大された。 2011年の東日本大震災後、ファミリーマート、ローソン、セブンイレブンの3大コンビニエンスストアグループの東北地方の店舗の80%が2週間以内に通常営業を再開し、災害支援に重要な役割を果たした。 セブンイレブンは地震発生後、速やかに災害支援本部を設置し、被災地で営業している店舗に1日3回商品を配送した。店舗の被害がひどく営業できない店主には移動販売車を提供し、被災者への最大限の支援に努めました。 ローソン北東部支店は緊急計画を開始し、被災地域の店舗が必要な物資の量を独自に決定できるようにした。同社は、関連する需給情報を継続的に収集するとともに、他の地域から原材料を動員して現地の工場に届け、生産・操業の再開を加速させている。 「被災地のローソンでは、まず店内の照明を点灯することから始めます」と、今年1月の能登半島地震後、被災地のローソン店長を務める神沢さんは言う。 「人命が第一であり、コンビニエンスストアをオープンすることで、地域に住む人々に安心感を与えることができると信じています。」 「正直、私たちも不安でした。でも、当社では年に3回防災訓練を行っています。災害が発生して避難指示が出たら、まずは自分たちが避難すること。地震の翌日には、社員だけでなくオーナーや関係者の安否も確認し、改めて備えの大切さを確認しました!」ローソンセントラルカンパニーの田上弘樹マネージャーはこう語った。 日本は2017年7月1日から最新の「災害対策基本法」を公布し、イオングループやセブン&アイ・ホールディングス(セブンイレブンの親会社)などスーパーやコンビニエンスストアを展開する7社が災害物資輸送拠点に加わることとなった。 過去には、このリストには電力や通信などの企業が含まれていました。日本が小売業を調査対象に加えるのは今回が初めて。自然災害により道路渋滞が発生した場合、これらの企業の資材トラックが真っ先に被災地に入り、災害救助に協力することができます。 1974年の「元年」から現在まで、日本のコンビニエンスストアは半世紀を歩んできました。モバイル端末への依存度が高まり、食生活も変化する中、人々は時代の流れに遅れないよう積極的に変化を求めています。 セブンイレブンは、ネット注文後30分以内の配達に注力する宅配サービス「7NOW」を積極的に展開している。ローソンはUberEatsを含む配達会社4社とも提携し、一部店舗で即時配達サービスも提供している。なお、ローソンの一部店舗では、従来の飲食スペースを廃止したため、UberEatsなどのプラットフォームと連携し、店内で調理済みの料理を配達するサービスが増えている。 同時に、ファミリーマートやセブンイレブンも自社の店舗網を活用し、広告・メディア事業を積極的に展開した。ファミリーマートは親会社の伊藤忠商事と2021年9月に運営会社ゲートワンを設立し、店舗内にAIカメラを搭載した大型デジタルビジョン「FamilyMartVision」を設置することを目指している。こうした大型スクリーンを設置した店舗では、広告商品の購入が平均で約20%、最大で約70%増加したという。 より「専門的」なカテゴリーを持つコンビニエンスストアも登場している。今年2月29日、東京近郊の千葉県松戸市に、セブンイレブンの画期的なコンビニエンスストア「SIPストア」第1号店がオープンした。 生鮮食品を中心に販売しているコンビニエンスストアです。面積は一般的なコンビニエンスストアの約1.8倍。姉妹会社であるイトーヨーカ堂の経営経験や輸送ネットワークを活用し、青果、肉、魚を中心とした生鮮食品、日用品、冷凍食品、加工食品を中心に販売しております。 同時に、主婦や高齢者に人気のロフト(日用品中心)や赤ちゃん本舗(母子用品中心)の商品も販売しています。 小さなコンビニエンスストアは日本人の日常生活を支えています。 |
<<: 基本的な運営業務内容(北京市西城区人民政府天橋街道事務所社会事業サービスセンターの運営に関する競争コンサルティング)
>>: ホームファニシングブランドのマーケティング計画(11年間の努力、Gujia Home Furnishingの「民に利益をもたらし、再生する」知恵が「家を愛する」という理念を継承)
推薦する
ケータリングブランドNo.1のマーケティングプランニング(マーケティングプランニングの専門家、葉茂中氏:実践的なヒント!地元ケータリングブランドNo.1を築く7つのステップ)
マーケティングプランニングの専門家、Ye Maozhong氏:実践的なヒント!地元でトップのケータリ...
酒類ブランドのマーケティング事例(湖北市場が躍進、楊韶酒類の国営化の旅が本格始動!)
湖北市場に出航、楊韶ワイン産業の国有化の旅が加速します! 6月28日午後、武漢でワイン業界のイベン...
一般的なサーバーやウェブサイト向けの推奨オンライン速度テストツールとPingツール
日々の仕事では、サーバーやウェブサイトのパフォーマンスと速度を評価する必要がある場合があります。テス...
より良いブランド企画会社(国内火鍋レストランデザイン/火鍋レストラン装飾デザイン強み会社ランキング!)
国内の火鍋レストランデザイン/火鍋レストラン装飾デザイン会社ランキング!出典: 36Krニュース国...
情報フロー広告メディア(情報フロー広告の三つ巴の交差点、それぞれ異なる大手が袂を分かつ)
情報流通広告の岐路、明確な区分を持つ大手各社が別々の道を歩む画像ソース @Visual China最...
ニューメディア運営の評価内容(亳州市政務開示事務所による2023年市全体の政務開示、政府ウェブサイト、政務ニューメディアの評価実施に関する通知)
亳州市政務開示事務所による2023年の市政務開示、政府ウェブサイト、政務新メディアの評価に関する通...
ビッグデータ運用とはどのようなことを行うのか (ビッグデータ エンジニアは何を行うのか? どのようなスキルを習得する必要があるのか?)
ビッグデータエンジニアは何をしますか?どのようなスキルが必要ですか?ビッグデータ エンジニアには多く...
資本運用の内容を簡単に説明します(資本運用とは?)
資本運用とは何ですか?資本とは、生産に使われる基本的な生産要素、つまり資金、工場、設備、資材などの物...
ウェブサイトをホームページに最適化する方法(ホームページに素早く到達するためのウェブサイト最適化の 6 つのテクニック)
ホームページに素早くアクセスするためのウェブサイト最適化の 6 つのテクニックウェブサイトをいかに...
ブランド企画コンテスト(朗報!金城の教師と生徒がグローバルブランド企画コンテストの決勝で「金賞」を受賞しました!)
良いニュースです!金城の教師と生徒が世界ブランド企画コンペティションの決勝で「金賞」を獲得しました!...
フランチャイズ情報フロー広告(ハンバーガーフランチャイズ業界は、Douyin情報フロー広告をうまく配置するにはどうすればよいでしょうか?)
ハンバーガーフランチャイズ業界は、Douyin 情報フロー広告を効果的に配置するにはどうすればよいで...
ac ドメイン名はどういう意味ですか? acドメイン名登録ルール
c ドメイン名は、アフリカに近い南大西洋に位置するイギリスの植民地であるアセンション島に属しています...
事業運営データ指標(電子商取引製品が注目すべき5つの主要運営指標)
電子商取引製品が注目すべき 5 つの運用指標電子商取引プラットフォームは数多く存在し、データに基づい...
アダルト商品のプロモーション手法(あなたの知らない「アダルト商品暴利プロモーション」の新モデル)
あなたの知らない「アダルトグッズ暴利販促」の新モデルここ数日、エージェントになるにはどうしたらよいか...
江蘇省の小規模工業塩メーカーの販売状況(塩化学大手、蘇岩井神:地域主導のパターンが形成され、塩製品の収益性が安定している)
塩・化学大手の蘇岩井神:地域主導のパターンが形成され、塩製品の収益性が安定(レポート作成者/アナリス...