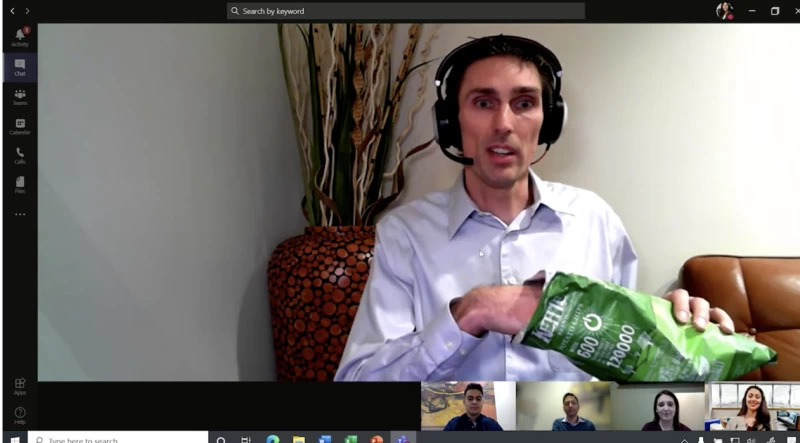ジョージ・フロイド氏とブレオナ・テイラー氏の死を受けて、米国は警察改革に注力している。検討されている新たな対策の一つに、警察官が装着するカメラへの重点化がある。実際、月曜日に民主党議員らが提出した新たな法案では、この技術への支援が重要なポイントとなっている。
2020年警察正義法は、「連邦制服警官にボディカメラの着用を義務付ける」ものです。また、「州および地方の法執行機関に対し、警察のボディカメラの使用を確実にするために、既存の連邦資金を活用すること」を義務付けます。
過去10年間に民間人の死亡が相次いだことを受け、米国の警察はボディカメラの導入を一斉に進めた。警察官は通常、胸部に装着し、一般市民と接する際には電源のオン・オフを切り替える必要がある。ボディカメラは、警察の透明性を高め、地域社会の信頼を高め、警察官の責任を問う、さらには武力行使の削減にもつながる可能性のある技術として高く評価されてきたが、こうした難題に対するボディカメラの役割は依然として不明確である。立法府が警察活動におけるボディカメラのシステム化を推進する中で、その有効性に関するデータがどのような結果をもたらすのか、またどのような結果に繋がらないのかを注視することは重要である。
ぼんやりとした絵
アメリカの法執行機関におけるボディカメラの使用の転機となったのは、2014年にミズーリ州ファーガソンで警察官が黒人の少年マイケル・ブラウンを射殺した事件だ。同年、ブラウンの家族は「将来はすべての警察官が」カメラを装着すべきだと述べ、オバマ政権は国全体でこの技術を推進するために数百万ドルの連邦資金を支給するに至った。2016年に司法省が実施した調査によると、米国の警察署(合計1万5000以上)の約47%が警察官にカメラを装着させている。「その数は大幅に増加しているのではないかと思う」と『Cops, Cameras, and Crisis』の共著者であるマイケル・D・ホワイトは言う。 「特に大規模な機関では、カメラの装着は日常的かつ仕事の一部となっており、警察官が携行する装備品のひとつに過ぎない」
デジタル製品もあります。「映像の大部分は公開されることはありません」と、『警官、カメラ、そして危機』の共著者でもあるアイリ・マルムは述べています。一般市民が膨大な映像にアクセスできるかどうか、またどのようにアクセスできるかは、地域の政策次第です。さらに、無数の人々がポケットにスマートフォンを持ち歩いていることを考えると、記録源は他にもある可能性があります。フロイド氏の死の際、メディアが共有した動画には、傍観者の映像、監視カメラの映像、ボディカメラの映像が含まれていました。
カメラが実際に警察の武力行使の削減につながるかどうかは、はっきりしない。2015年から2016年にかけてワシントンD.C.で行われたある有名な実験では、同市の警視庁の警官の半数が7ヶ月間ボディカメラを装着した。残りの半数は装着しなかった。「私たちが得た主要な結果は、武力行使の可能性や苦情の発生率に、有意で検出可能な影響は見られなかったということです」と、ブラウン大学政策研究所所長で、このランダム化研究の主任科学者であるデイビッド・ヨーカム氏は述べている。
警官への苦情申し立てといった具体的な指標に関しては、ヨクム氏のチームは、研究のウェブサイトにあるように、カメラによる「検知可能な影響」は見られなかったと結論付けている。「要するに、ボディカメラ技術がどのような影響を与えるのかという期待を再考する必要があるということです」と彼は振り返る。「警察署長であれば所属する警察組織に対して、一般住民であれば地域社会に対してです。」
だからといって、警察がボディカメラの使用を自動的に拒否すべきではないとヨクム氏は言う。もしボディカメラが現場装備の一部となるのであれば、それは安全性と透明性の向上に向けた取り組みの一つの要素に過ぎないはずだ。「カメラは、警察のスキルセットと文化に影響を与える無数の要素の一つに過ぎません」と彼は指摘する。
さらに静的
ヨクムの調査結果を裏付ける研究が他にもある。オハイオ州立大学の公共政策学助教授で、警察と地域社会の関係性を研究しているアンドレア・ヘッドリー氏は、フロリダ州ハランデールビーチにおけるボディカメラに関する研究の筆頭著者だ。「いずれの結果も統計的に有意な結果には達しませんでした」とヘッドリー氏は述べているが、データには統計的に有意ではない傾向も見られた。例えば、ボディカメラを着用した警官は、着用していない警官よりも多くの違反切符を交付したという。
ヘッドリー氏と同僚が近々発表する別の研究では、ワシントンD.C.の住民にインタビューを行い、この技術に対する彼らの意見を集めました。「私たちは特に有色人種の住民に焦点を当てました」とヘッドリー氏は言います。「彼らはボディカメラが警察官の行動に影響を与える可能性があると考えていましたが、それが信頼を高め、警察と地域社会の関係を構築するとは考えていなかったのです。」
しかし、ヨーカム氏と同様に、ヘッドリー氏もこの技術を完全に否定しているわけではない。彼女は、ボディカメラは万能薬ではなく、各部署がどのように導入するかが重要だと指摘する。「私にとって重要なのは、ボディカメラは透明性や説明責任を実現するためのツールの一つに過ぎないということです。人種的偏見や人種間の格差といった根深い問題を解決するという点では、ボディカメラは解決策にはならないと思います。」
しかし、すべてのレビューがこのように賛否両論というわけではない。ホワイト氏とマルム氏は、数十件の発表済み研究を分析した結果、いくつかの傾向が浮かび上がってきたと述べている。「これまでで最も一貫した結果は苦情に関するものです」とマルム氏は言う。26件の研究のうち20件で、警察官がカメラを装着すると警察に対する苦情が減少することが明らかになっている。ホワイト氏はさらに、カメラの存在がいわゆる「軽薄な」、つまり根拠のない苦情を減らす可能性もあると付け加えた。
万能薬ではない
カメラシステムも決して安くはありません。「本当のコストは後工程にあります」とホワイト氏は言います。映像のデジタル保存にかかる予算は、ハードウェア本体よりも多くの部署予算を圧迫する可能性があるからです。このシステムで最も人気の高い小売業者の一つは、テーザー銃も製造しているアクソン社です。
結局のところ、明確な映像証拠の存在は、必ずしも偏見を解消したり、事件を解決したりするものではありません。「映像は以前にもありました」と、ノースイースタン大学犯罪学・刑事司法学部のロッド・ブランソン教授は、ロドニー・キング事件とエリック・ガーナー事件の両方を挙げて述べています。「事件の映像や写真があれば得られると思われるような確信は得られません。一部の人々の見解では、必ずしも公正な正義の実現につながっているわけではありません。」
「有色人種の人たちは、直接体験したことや、家族や他のコミュニティのメンバーからの間接的な体験を確認するためにカメラを必要としません」と彼は付け加えた。