
1970年代、ポリネシア航海協会は、伝統的な航海技術のみを用いてハワイからタヒチまで航海することを目的としたポリネシア航海カヌーを建造し、進水させました。「ホクレア」と名付けられたこのカヌーは、カロリン諸島出身の航海士マウ・ピアイルグによって操縦されました。このプロジェクトの目的は、数百年もの間そのような航海は行われていなかったものの、古代ポリネシアの航海者たちは風、海、星に関する知識のみを頼りに2,500マイル(約4,000キロメートル)以上もの距離を航海することができたということを示すことでした。
1976年5月1日、ホクレア号はマウイ島を出航しました。出航直前、マウは乗組員たちに演説を行い、海上での行動指針を説きました。「出航する前に、心配事はすべて捨て去ってください。すべての悩みは陸に置いてきてください」と彼は言いました。海上では「私たちの行動はすべて異なります」と彼は言いました。乗組員は常に船長の指示に従います。「船長が『食べろ』と言ったら食べ、船長が『飲め』と言ったら飲む」。3週間、あるいは4週間、彼らは陸地から遠く離れた場所に滞在することになります。「私たちが生き延びるために必要なのは、持参した物だけです。……皆さん、これらの物を忘れないでください」と彼は締めくくりました。「そうすれば、私たちは目的地にたどり着くでしょう」
船には、カパフレフア船長とマウに加え、航海の記録係であるベン・フィニーと、マウの航海の記録係であるデイビッド・ルイスが乗船していた。トミー・ホームズも乗組員として航海に同行し、豚、犬、そして「本物のモア」(鶏)といった動物たち、そして様々な根菜、挿し木、苗木の世話をするという特別な任務を負っていた。これらは湿った苔、マット、タパ布で包み、海水から守られていた。トラブル発生時に備えてカヌーに随伴し、後にマウの日々の推定と照合するための詳細な位置記録を保管していたのは、全長64フィートのケッチ「メオタイ」だった。
航海における主な課題は、南への長旅の間、カヌーを十分東に寄せておくことだった。ハワイはタヒチの北2,600マイル以上離れているが、西に約500マイルも離れている。航路沿いの風は主に東からの風で、赤道上では北東、赤道下では南東の風が吹く。これに西向きの潮流が加わり、問題は明らかだった。「我々の戦略は」とフィニーは記している。「カヌーがあまり速度を落とさずに、できるだけ風上に向かって航行し、その後はできるだけ東向きの方向を維持することだった」。最大の懸念は、タヒチの緯度に到達した時に、西に行き過ぎてしまい、目的地にたどり着くには風上に戻らなければならないことだった。
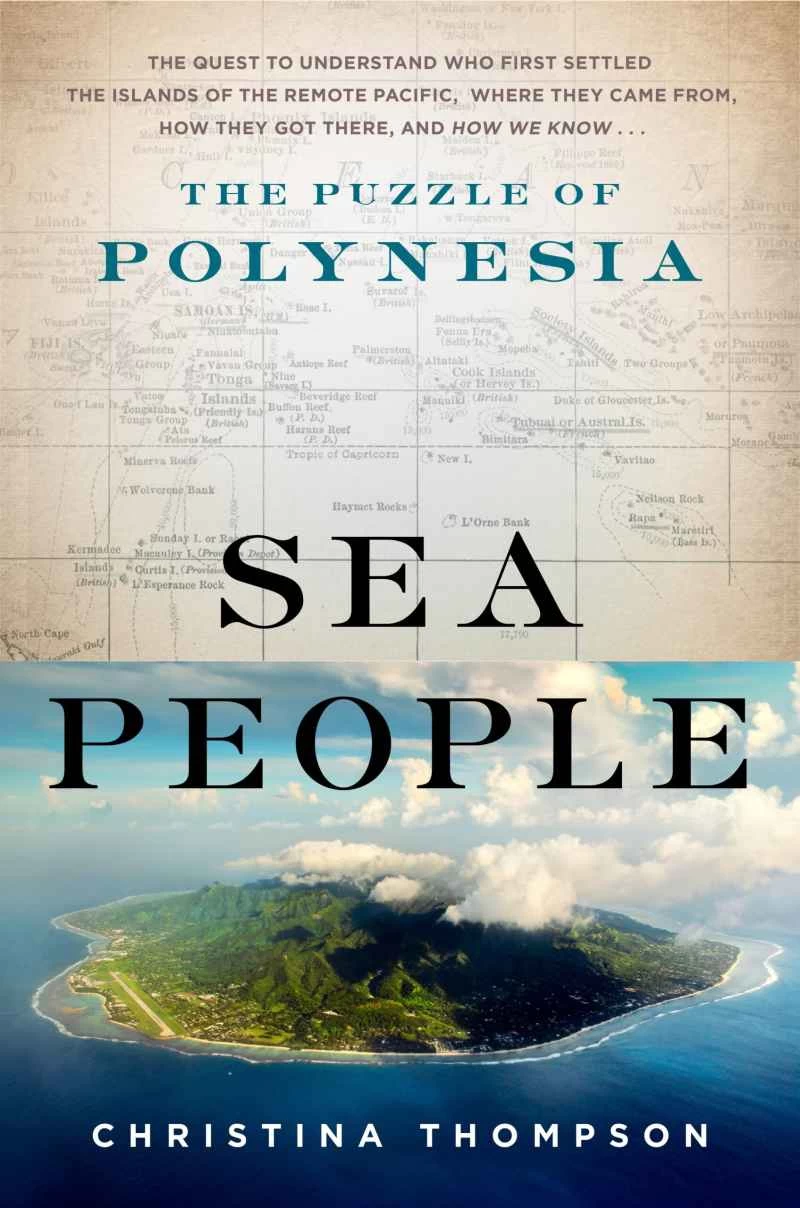
最大の未知数の一つは、マウにとって全く未知の航路であったことを考えると、彼の航海知識が十分であったかどうかだった。「中世のタヒチやハワイの航海士は、ピアイルグが自国や近隣の群島について持っていたのと全く同等の情報をハワイ・タヒチ航路について持っていたはずだ」とルイスは記している。彼は星の軌道、遭遇する可能性のある風や海流、そして一日の航海で通常進む距離を知っていたはずだ。いわば、彼は自分の地元を航海していたと言えるだろう。しかしマウは太平洋の全く異なる地域、はるか西の出身であり、空も海も気象パターンも全く異なっていた。そして、彼の経験は、この航海の過程で横断する緯度の一部しかカバーしていなかった。この最後の緯度は航海に大きな意味を持っていた。例えば、北極星はカロリン諸島の航海では重要な役割を果たしたが、赤道より下ではもはや見えなくなっている。そのため、南半球に渡った途端、マウは重要な天体の基準点を失うことになる。ルイスの仕事の一つは、マウの地理知識の必然的な欠落を埋めるのを手伝うことだった。その方法の一つが、ビショップ博物館のプラネタリウムを訪れることだった。そこで彼らは星投影機を使い、カヌーが北半球から南半球へ航行するにつれて夜空がどのように変化するかをシミュレートした。「この背景が明らかになると、マウは航海の戦略を定めた。エタック(マルケサス諸島)と、辿るべき星の航路だ」とルイスは記している。
ハワイ諸島を離れると、マウは東南東の方向に舵を取り、さそり座の「赤色巨星」アンタレスの昇る点を目指した。アンタレスはポリネシア人には「マウイの釣り針」として知られている。空と海を見つめるマウを見ていたフィニーは、熟練の航海士の仕事ぶりを見られるのは「めったにない特権」だったと形容した。人類学者のトーマス・グラッドウィンは、カロライナの航海士たちは航海中、常に油断なく気を配っていたと観察していた。「経験豊富な航海士は血走った目で見分けられると言われている」と彼は書いている。マウは「その役にふさわしい風貌だ」とフィニーは思った。ほとんど眠ることはなく、ときどきうたた寝をするだけだった。「ほとんどの時間、デッキの手すりに寄りかかって立っていたり、手すりの上に腰掛けて海や帆、夜には星を眺めていた」
乗船者の中にはマウ、カウィカ、ルイス、フィニーといった熟練の船乗りもいたが、乗組員の多くはハワイで「ウォーターマン」と呼ばれる、サーファー、パドラー、ライフガードなどの職業に就いていた。彼らは泳ぎが上手で力持ちで海にも慣れていたが、職業的に船員を務めたことや長距離を航海したことはなかった。出航してわずか 6 日後、そのうちの 1 人が「おい、もうすぐ着くのか?」と尋ねて交代した船長を驚かせた。実際には、再び陸地を見るまで 3 週間以上もかかることになる。無風状態が長く続き、風向きが不安定で波が立つ時期と、波が穏やかな時期があった。ある記録員が「銅のような太陽の下、波打つ水銀の巨大な皮膜のように滑らかだった」と表現した海は、状況をさらに悪化させた。乗組員の 1 人はほぼ緊張病状態に陥り、他の乗組員は不機嫌に陥った。
目標に近づくにつれ、ルイスは西へ行き過ぎたのではないかと不安になり始めた。しかし、マウは「冷静に自信に満ちている」ように見え、航海の30日目には翌日にはツアモツ諸島に到着するだろうと予言した。それから間もなく、乗組員の一人がシロクロアジサシを数羽発見した。すると、いつもの貿易風のうねりが弱まった。「そこに島がある」とフィニーは記した。「しかし、どの島だ? どれくらい遠いんだ?」翌日、ホクレア号はツアモツ諸島の北西端、タヒチの北320キロ足らずにあるマタイバ島に上陸した。
ホクレア号は6月4日の朝、タヒチの首都パペーテに到着した。世界各地との無線通信が途絶えていた乗組員たちは知らなかったが、タヒチの人々は熱心にホクレア号の進路を見守っていた。街中に貼られた海図にカヌーの毎日の位置情報を掲載し、新聞、ラジオ、テレビで状況を報告していたのだ。フランス領ポリネシアの総督は、彼らが到着した日を祝日と宣言していた。学校や企業は休校となり、港には何百隻ものカヌー、ランチ、ヨットが停泊していた。前夜から人々は港に集まり始めており、カヌーが到着する頃には「人々は至る所にいた。波に膝まで浸かり、岩礁を越え、岸辺に押し寄せ、水辺の建物の上にとまり、水辺の木々の枝を押さえていた」とフィニーは書いている。 1万7000人以上、島民の半数以上がホクレア号の到着を見届けようと集まっていた。岸辺では歓声と太鼓の音が響き渡っていたが、カヌーが近づくと群衆は静まり返り、教会の聖歌隊がこの日のために特別に作曲されたタヒチの歓迎の賛美歌を歌い上げた。数千人が合唱に加わった時の感動は、ある目撃者の記憶によると「背筋が凍るような」ものだったという。
クリスティーナ・トンプソン著『Sea People: The Puzzle of Polynesia』より、ハーパーコリンズの許可を得て掲載。
