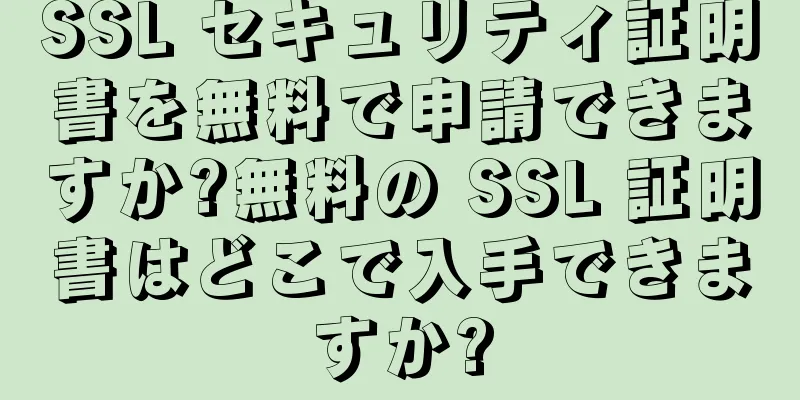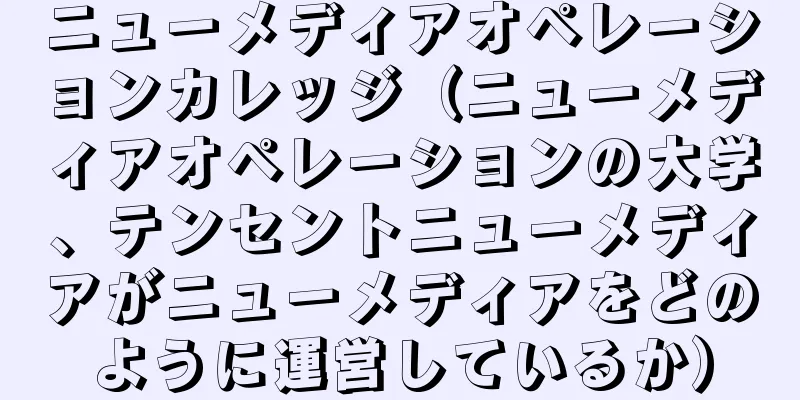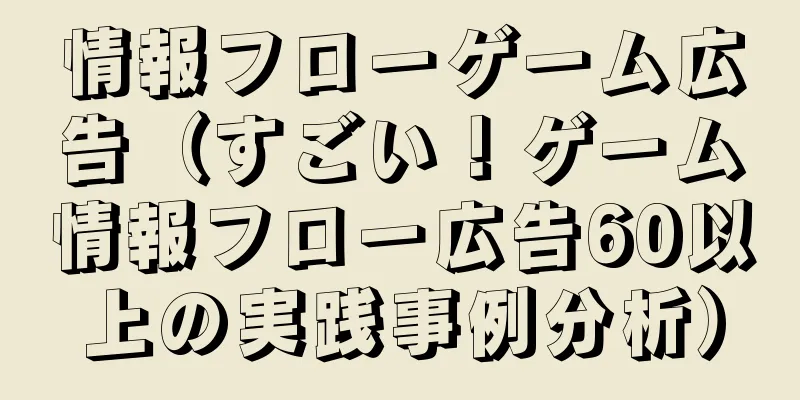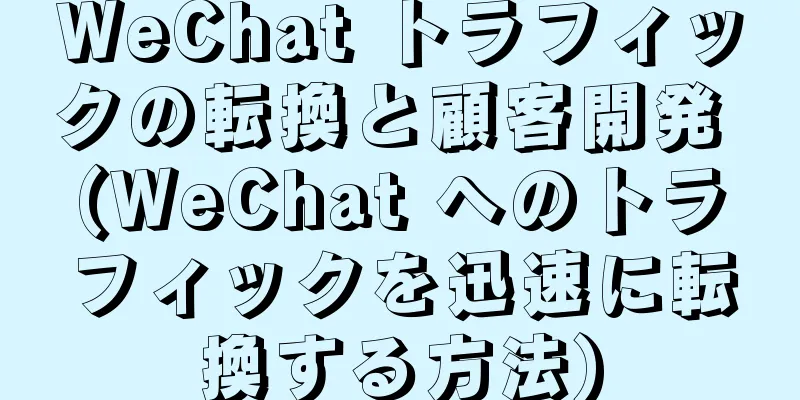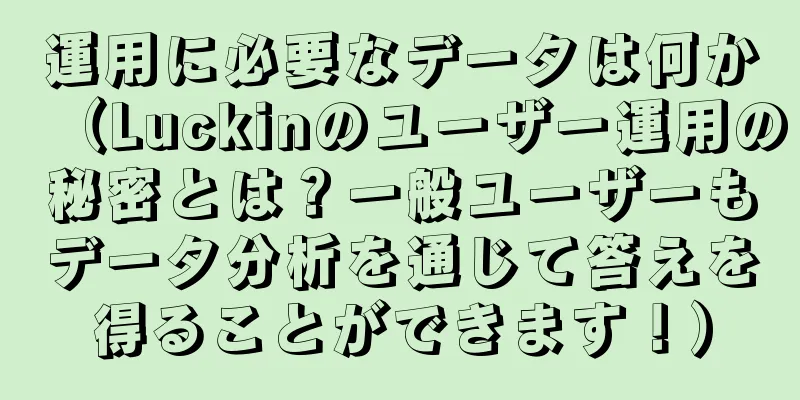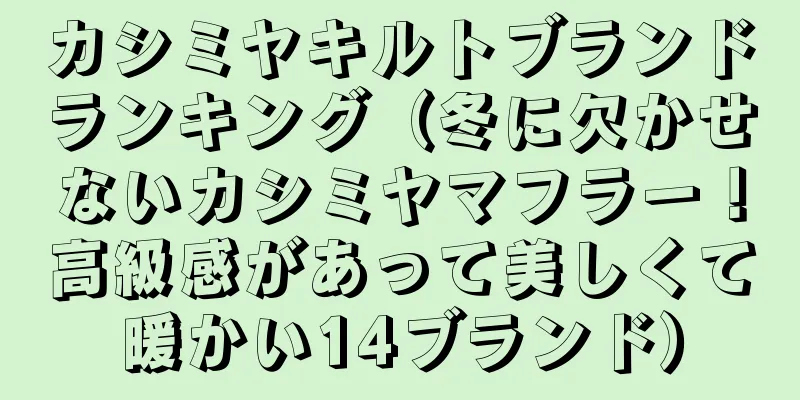ウィーメディア運営サービスの内容(長編・短編動画の著作権侵害紛争におけるネットワークプラットフォーム事業者の責任)

長編・短編動画の著作権侵害紛争におけるインターネットプラットフォーム運営者の責任モバイルインターネット技術とスマートネットワーク端末の普及に伴い、低コストで拡散しやすい短編動画は、ユーザーの消費嗜好の変化に適応したユーザー生成・無料共有の配信モデルを採用し、長編動画の本来の配信モデルと市場構造に直接挑戦しています。長編・短編動画をめぐるオンライン市場の競争は、動画著作権侵害紛争という形で訴訟プロセスに突入しました。インターネットプラットフォームは、ビデオネットワークの配信に不可欠かつ必要な施設であり、中心的な役割を果たしています。このため、動画ネットワークをめぐる著作権侵害紛争の場合には、長時間動画の権利者がネットワークプラットフォーム運営者を直接被告として挙げ、著作権侵害の責任を負わせるケースが多い。そのためには、動画ネットワーク著作権侵害紛争におけるネットワークプラットフォーム事業者の責任について研究し、明確にする必要がある。 1. オンライン動画プラットフォーム運営者の優位性 インターネットは情報の伝達方法に革命をもたらし、人間の情報交換に大きな影響を与えました。インターネット技術の反復的な進化により、ネットワーク情報の伝達方法もさらに変化しました。 Web 1.0 の時代では、ウェブサイトはオンライン情報を発信するための主なプラットフォームです。ウェブサイト運営者は、インターネット情報の提供者として、テキスト、画像、動画、音声などのインターネット情報を編集・整理し、ウェブサイトを通じてユーザーに提供します。ユーザーはウェブサイトにアクセスしてインターネット コンテンツを取得します。ウェブサイト運営者はネットワーク サービス プロバイダーであると同時にネットワーク情報プロバイダーでもあり、ユーザーは単にネットワーク情報の受信者です。書籍出版社や新聞社などのウェブサイト運営者は、一般の人々にさまざまな情報を提供しています。 Web 2.0 時代では、ネットワーク通信技術の発展により、ネットワーク情報伝送のインタラクティブ性が実現され、ユーザーはネットワーク プラットフォームを使用してインタラクティブに情報を交換できるようになりました。同じネットワーク プラットフォーム上のユーザーは、ネットワーク プラットフォームを通じて他のユーザーが提供する情報を取得したり、ネットワーク プラットフォームを通じて他のユーザーに情報を提供したりできます。インターネット ユーザーは、インターネット情報の受信者であると同時に提供者でもあります。もちろん、ネットワークプラットフォーム運営者は、プラットフォーム上でネットワークユーザーにさまざまな情報を提供することもできます。将来の Web3.0 は、新しい分散型サイバースペースのビジョンを形成します。このビジョンでは、すべてのネットワーク ユーザーが自分のネットワーク情報の管理者になりますが、Web2.0 時代と同様に、ユーザーはネットワーク情報の受信者と提供者の両方になります。現在、インターネットはWeb2.0からWeb3.0へと進化する傾向にありますが、依然としてWeb2.0が主流となっています。 特にオンラインビデオの分野では、現在、長編ビデオ、中編ビデオ、短編ビデオが並行して発展する傾向が見られます。その中で、テレビドラマ、映画、ドキュメンタリー、イベント番組、バラエティ番組などに代表される長編動画は、オンラインプラットフォームの運営者によってオンラインプラットフォームにアップロードされるものがほとんどで、ユーザーはオンラインプラットフォーム上で視聴することを選択できます。この場合、ネットワークプラットフォーム事業者は、ネットワークサービスプロバイダーであると同時にネットワークコンテンツプロバイダーでもあり、これは前述のWeb 1.0時代のネットワーク情報生成・伝送モデルの特徴と一致しています。短編動画は主にインターネットユーザーによってオンラインプラットフォームにアップロードされ、オンラインプラットフォームを通じてプラットフォーム上の他のユーザーが視聴できます。この場合、ネットワークプラットフォーム事業者はネットワークサービスプロバイダーであり、ネットワーク利用者はネットワークコンテンツプロバイダーであり、これは前述のWeb 2.0時代のネットワーク情報生成・伝送モデルの特徴と一致しています。中程度の長さの動画のブームにより、長い動画は長すぎる、短い動画は短すぎるという欠点が克服されました。コンテンツの完成度が高く、論理的な一貫性が強く、インターネット ユーザーの消費嗜好に沿ったものとなっています。長い動画も短い動画も、中くらいの長さの動画へと進化しています。現在、従来の長編動画プラットフォームと新興の短編動画プラットフォームは、長編動画、中編動画、短編動画を同時にユーザーに提供しています。オンライン ビデオ プラットフォームの運営者は、ネットワーク サービス プロバイダー、ネットワーク コンテンツ プロバイダー、またはその両方である場合があります。 民法、情報ネットワーク通信権保護条例などの関連法律規定によれば、ネットワークコンテンツプロバイダーとネットワークサービスプロバイダーの著作権侵害責任は同じではありません。インターネットコンテンツプロバイダーは著作権侵害に対して直接的な責任を負う一方、インターネットサービスプロバイダーは著作権侵害に対して間接的な責任を負うことになります。したがって、オンライン ビデオに関する著作権紛争では、関係するビデオが一般に公開されている場合、関係するビデオのネットワーク サービス プロバイダーが誰であるか、関係するビデオのネットワーク コンテンツ プロバイダーが誰であるか、またはその両方であるかを特定する必要があります。 II.オンライン動画プラットフォーム運営者による直接侵害 著作権は法的排他的権利であり、本質的には作品に関わるさまざまな法的行為に対する独占的管理です。それぞれの特定の権利は、特定の独占的管理行動に対応します。例えば、複製権は著作物の複製に対する支配を独占する行為であり、情報ネットワーク伝達権は著作物のネットワーク伝達に対する支配を独占する行為です。著作権者の許可なく、著作権者が管理する法定行為を1つ以上行うと、法定免除がない限り著作権侵害となります。このような著作権侵害は理論的には直接的な著作権侵害と呼ばれます。個別のケースでは、関係するビデオが一般に公開されている場合、裁判所はオンラインビデオプラットフォームの運営者がネットワークコンテンツプロバイダーであるかどうかを検討する必要があります。 1. オンライン動画プラットフォームの運営者が自ら短編動画を提供し、他人の長編動画の著作権を侵害した場合、オンライン動画プラットフォームの運営者はオンラインコンテンツの提供者であり、直接的な著作権侵害に該当します。上記の直接著作権侵害の定義によれば、ネットワークビデオプラットフォーム運営者が自らが管理・運営するネットワークプラットフォームを通じて提供する短編動画が他人の長編動画の著作権を侵害し、法定免責事由がない場合は、原則として直接著作権侵害を構成するとみなされる。例えば、オンライン動画プラットフォームの運営者が、他人の長編動画の著作権を侵害する短編動画を自社のプラットフォームにアップロードし、公衆が閲覧可能な状態に置いた場合、直接的な著作権侵害に当たると判断される。例えば、オンライン動画プラットフォームの運営者が、他人の長編動画の著作権を侵害する短編動画をインターネット上に自発的に保存し、公衆が閲覧可能な状態に置いた場合、直接的な著作権侵害に当たると判断されるはずです。また、例えば、権利者がインターネットを通じて動画を公衆に提供し、オンライン動画プラットフォームの運営者が技術的手段を採用して動画の提供を実質的に代替した場合も、原則として著作権の直接侵害に当たるとみなされる。 2. ネットワークビデオプラットフォーム運営者とユーザーが共同で提供する短編動画が他人の長編動画の著作権を侵害した場合、ネットワークビデオプラットフォーム運営者はネットワークコンテンツプロバイダーであり、直接の侵害を構成する。オンライン動画プラットフォーム運営者とそのユーザーは、分業と協力を通じて、オンライン動画プラットフォームを通じて短編動画を共同で一般に提供します。オンライン動画プラットフォーム運営者とそのユーザーの行為が両方とも直接侵害を構成するために不可欠である場合、両者は共同侵害を構成し、両方とも直接侵害となります。オンライン動画プラットフォームの運営者とそのユーザーの間で共同侵害を犯す意図について事前に連絡があったかどうかは、共同侵害の判断に影響を与えません。しかし、オンライン動画プラットフォームの運営者は、伝統的な出版分野の「編集管理基準」に沿って、短編動画コンテンツに意識的に介入し、管理する必要があることを指摘しておく必要がある。したがって、オンライン動画プラットフォームの運営者が、自動化されたネットワークアクセス、送信、保存、検索、リンク、共有などのネットワーク技術サービスを提供するだけであれば、その行為は共同侵害を構成するとはみなされず、また、その行為のみが直接侵害を構成するともみなされない。 III.オンライン動画プラットフォーム運営者による間接侵害 間接侵害は直接侵害と相対的なものです。間接的な著作権侵害とは、簡単に言えば、教唆や幇助など、他人が直接的な著作権侵害を犯すように誘導する行為を指します。間接的な著作権侵害は、直接的な著作権侵害を前提としています。直接的な著作権侵害が成立しない場合は、間接的な著作権侵害も成立しません。間接著作権侵害には特定の構成要素があるため、直接著作権侵害が成立した場合、間接著作権侵害は成立しない可能性があります。 間接侵害は、本質的には責任の対象に関する特別な規定です。直接侵害者の不法行為に対して間接侵害者にも不法行為責任を負わせる法制度です。民法は、インターネットサービスプロバイダーに対して、「知っていた、または知っているべきであった」という主観的基準に基づいて間接不法行為責任制度を規定しています。オンライン動画の著作権侵害紛争について具体的に言えば、オンライン動画プラットフォームの運営者がネットワークサービスプロバイダーとして、そのユーザーが提供する短編動画が他人の長編動画の著作権を侵害していることを知っている、または知っているべきである場合、オンライン動画プラットフォームの運営者は間接侵害を構成することになります。 1. オンライン動画プラットフォームの運営者が「知っていた」かどうかの具体的な判断。 「知る」とは、実際の知識と一定の認識の事実上の状態を指すはずです。長編動画の権利保有者が通知を送信し、オンライン動画プラットフォーム運営者が通知を受け取った後、事実関係が「知らない」から「知っている」に変わります。したがって、長編動画の権利者から送られた通知は、オンライン動画プラットフォームの運営者が「知っている」かどうかを判断するための主な証拠となります。通知には、侵害の予備的証拠および権利者の真の身元情報が含まれ、この情報は十分かつ正確でなければなりません。オンラインビデオプラットフォームの運営者は、さらなる調査を行う必要はありません。通知自体に基づいて、特定のユーザーがオンラインビデオプラットフォームを通じて公衆に提供した通知に記載された特定のビデオが、長編ビデオの権利者の著作権を侵害していると判断できます。したがって、オンライン動画プラットフォームの運営者が個別の事例において「知っていた」かどうかを判断する際には、以下の3つの点にも留意する必要がある。 まず、オンライン動画プラットフォームの運営者が技術的、自動化された受動的なネットワークサービスのみを提供し、動画のアップロードや共有などのユーザーのオンライン行動を実際に制御しておらず、ユーザーがアップロードして共有した動画の具体的な内容を把握していない場合、オンライン動画プラットフォームの運営者は、ユーザーがプラットフォーム上で提供した短編動画が他人の長編動画の著作権を侵害していることを「知っている」と判断されるべきではありません。 第二に、「知る」という内容は具体的かつ具体的でなければなりません。 「知っている」とは、オンライン動画プラットフォームの運営者が、プラットフォーム上でユーザーが公開する短編動画が他人の長編動画の著作権を侵害する可能性があることを、一般的かつ漠然と知っていることを意味するものではありません。 「知っている」とは、オンライン動画プラットフォームの運営者が、そのプラットフォーム上の特定のユーザーが他人の長編動画の著作権を侵害する短編動画をオンラインプラットフォームにアップロードし、公衆がアクセスできる状態に置いたことを確実に知っていることを意味するはずです。 さらに、「知っている」とは、オンライン動画プラットフォームの運営者が能動的ではなく受動的に知っていることを意味します。オンライン動画プラットフォームの運営者は、ショートビデオのアップロードや共有など、ユーザーのオンライン行動に対する一般的な事前監督義務を負っておらず、ユーザーがプラットフォームを使用して違法行為を行っていないかを積極的に審査する日常的な検査義務も負っていない。オンライン動画プラットフォーム運営者は、技術的な手段を使用して、ユーザーがプラットフォームにアップロードした短い動画を自動的にインデックス付けして分類し、検索を設定し、アルゴリズムによる推奨を使用します。オンライン動画プラットフォームの運営者が、これらの自動化された技術的操作に基づいて、プラットフォーム上でユーザーが提供した短編動画が他人の長編動画の著作権を侵害していることを知っていると想定するのは適切ではありません。 2. 「オンライン動画プラットフォーム運営者が知っておくべきこと」の具体的な応用。 「知っているべき」というのは本質的には注意義務です。 「知っているべきだった」のに実際には知らなかった場合、それは注意義務違反であり、民法上の過失を構成します。異なる主題基準によれば、注意義務は、一般人の注意義務、自分の事柄を処理する際に行使すべき注意義務、および善良な管理者の注意義務に大別できます。これらの注意義務に違反すると、それぞれ重過失、特定過失、抽象的過失となります。民法第1197条は、ネットワークサービス提供者に「知っているべき」という注意義務があることを明確に規定していますが、この注意義務の対象基準は規定されておらず、この注意義務の具体的な適用状況も規定されていません。 オンライン動画プラットフォーム運営者に対する「知っているべきだった」という要件は例外であり、特定の状況にのみ適用されるべきです。民法第1197条は、インターネットサービスプロバイダーが「知っている」または「知っているべきである」と規定していますが、「知っている」が原則であり、「知っているべきである」は例外であり、「知っているべきである」は特定の状況にのみ適用されるべきです。そうでなければ、「知っているべき」の適用状況が広すぎるため、注意義務の主観的過失の要素が弱まるか、あるいは軽視され、最終的にはオンライン動画プラットフォーム運営者の帰属原則が無過失原則に変わることになる。これは間接的な著作権侵害に対する過失責任の原則と明らかに矛盾しています。 「知っているべきであった」が適用される具体的な状況は、著作権侵害の事実が明白であるかどうかを中核基準として、著作権侵害の事実が明白な状況にのみ適用されるべきである。著作権侵害の事実が明白であるかどうかについては、一般人(インターネットユーザー)の注意義務の基準を採用することが適切である。 IV.オンライン動画プラットフォーム運営者の著作権侵害責任 前述のように、オンライン動画の著作権侵害に関わる紛争では、オンライン動画プラットフォームの運営者が直接的な著作権侵害または間接的な著作権侵害の責任を負う可能性があります。 1. オンライン動画プラットフォーム運営者の直接的な著作権侵害責任。オンラインコンテンツの提供者として、オンライン動画プラットフォーム運営者が提供する短編動画が他人の長編動画の著作権を侵害した場合、それは直接的な著作権侵害に該当します。したがって、長編動画の権利者が著作権を侵害されたと主張し、オンライン動画プラットフォームの運営者に著作権侵害の直接的な責任を負わせるよう要求する場合には、これを支持すべきである。 オンライン動画プラットフォームの運営者とそのユーザーが共同で提供する短編動画が他人の長編動画の著作権を侵害した場合、両者はオンラインコンテンツの提供者であり、両者とも直接的な侵害を構成し、共同で侵害を行っていることになります。民法第1168条によれば、二人以上の者が共同で侵害行為を行い他人に損害を与えた場合、連帯責任を負うことになる。これを踏まえると、オンライン動画プラットフォームの運営者とそのユーザーは、本件に関わる著作権侵害について連帯責任を負うべきである。したがって、長編動画の権利者が著作権を侵害されたと主張し、オンライン動画プラットフォームの運営者に著作権侵害の直接的な責任を負わせるよう要求する場合には、そのような要求は支持されるべきである。 2. オンライン動画プラットフォーム運営者の間接著作権侵害責任。民法第1195条によれば、インターネットサービスプロバイダーが通知を受けた後、適時に必要な措置を講じなかった場合、損害の拡大についてネットワークユーザーと連帯責任を負うことになる。ここでいう「ネットワークサービスプロバイダーが通知を受ける」とは、前述のネットワークサービスプロバイダーが、そのユーザーがネットワークプラットフォームを利用して侵害行為を行ったことを「知っている」とみなされるべきである。民法第1197条によれば、インターネットサービスプロバイダーは、そのユーザーがインターネットプラットフォームを利用して他人の民事権益を侵害していることを知り、または知るべきであったにもかかわらず、必要な措置を講じなかった場合、ユーザーと連帯責任を負うことになる。 「ネットワーク サービス プロバイダーが知っていた、または知っているべきだった」というフレーズについては、上で説明しました。 特に、オンラインビデオの著作権侵害紛争の場合、ネットワークサービスプロバイダーであるオンラインビデオプラットフォーム運営者が権利者からの通知を受け取った後、適時に必要な措置を講じなかった場合、損害の拡大についてユーザーと連帯責任を負うことになります。オンライン動画プラットフォームの運営者は、ネットワークサービスプロバイダーとして、そのユーザーが提供する短編動画が他人の長編動画の著作権を侵害していることを知り、または知るべきであったにもかかわらず、必要な措置を講じなかった場合、ユーザーと連帯責任を負うことになります。つまり、ユーザーの行為が直接的な著作権侵害を構成し、ネットワークビデオプラットフォーム運営者の行為が間接的な著作権侵害を構成する場合、ネットワークビデオプラットフォーム運営者とユーザーは連帯責任、つまり直接的な著作権侵害責任を負うことになります。 以上から、直接著作権侵害と間接著作権侵害の構成要素は異なるものの、ネットワークビデオプラットフォーム運営者の行為が直接侵害を構成するか間接侵害を構成するかにかかわらず、侵害責任の具体的な内容と負担方法に実質的な違いはなく、最終的には運営者が直接著作権侵害責任を負うことになることがわかります。 (著者所属:中国応用法学研究所インターネット司法研究センター所長 宋建宝) |
<<: ウィーメディアエージェンシー運営サービス内容(ドウインライフサービスは宿泊手数料率を4.5%から8%に引き上げます)
>>: ケーキブランド企画(どのアイスクリームケーキが一番美味しい?Yupinxuanが甘くて爽やかな楽しみをお届けします)
推薦する
自信ブランド企画(起業家の意見(6)丨良い品質は私たちの自信、良いブランドは私たちの東風)
起業家の意見(6)丨 良い品質は私たちの自信であり、良いブランドは私たちのサポートです【編集者注】中...
製品運用と新メディア運用(新メディアを活用して製品マーケティングを行うには?)
新しいメディアを活用して製品マーケティングを行うにはどうすればよいでしょうか?ご招待ありがとうござい...
運営費(張国東(東梁)コスト設計:プロジェクトコストの詳細な説明)
張国東(東梁)コスト設計:プロジェクトコストの詳細な説明建設費とは、建設プロジェクトを完了するために...
米国の VPS サーバーをレンタルすると、Web サイトの SEO に影響がありますか?
登録不要、コスト効率の高さ、管理のしやすさなどの利点から、多くのウェブマスターはアメリカのPSサーバ...
経営分析データ(2020年以降の商業銀行の経営状況と財務データ)
2020年以降の商業銀行の営業状況と財務データの完全な分析【文章】全体として、国立銀行は業務が徐々...
情報フロー広告業界(百度、微博、今日頭条は情報フロー広告戦争でどう戦うのか?)
情報流通広告戦争で、百度、微博、今日頭条はどう戦うのか?この問題は前のビデオで説明されました。時間は...
GlobalSign の単一ドメイン SSL 証明書の年間費用はいくらですか?
GloblSign は、WebTust によって認定されたデジタル証明書認証機関および SSL 証明...
運用データ アルゴリズム (Douyin 運用データ アルゴリズムとは)
Douyin 操作データ アルゴリズムとは何ですか? Douyinは現在最も人気のある短編動画プラ...
ビジネスデータ分析ppt(「元福道」製品分析:その背後にある動作ロジックの分析)
「元福道」製品分析:分析の背後にある動作ロジックこの度、新型コロナウイルスの影響により、文部科学省...
製品運用とは(製品運用の目的は何ですか?)
製品運用の目的は何ですか?インターネット製品担当者として、ビジネス パートナーとして (少なくとも私...
ブランド企画会社はどこにありますか(企業ウェブサイトの公開協力、ブランドマーケティングの企画、ソフト記事の公開に最適な会社はどこですか)
企業ウェブサイトの公開、ブランドマーケティングプランニング、ソフトコピーライティングの協力に最適な会...
家具製品のマーケティング(国産品の台頭による利益をいかに捉え、発展の勢いを解き放つか、リンズホームファニシングの「ダブルフェスティバルプロモーション」が国慶節の家具マーケティングのベンチマークとなる)
国産品の台頭による利益をいかに捉え、発展の勢いを解き放つか、リンズホームファニシングの「ダブルフェス...
製品運用機能(「インテリジェンス」が新たな広告手法を活用し、広告主に新たな機会が到来)
「インテリジェンス」は新しい広告手法を活用し、広告主に新たな機会をもたらしました著者 |張志白編集...
ブランド共同ブランディングマーケティング(2023年、国境を越えた共同ブランディングの5つの活用方法)
2023年、国境を越えたコラボレーションを実現する5つの方法今日では、共同ブランディングはブランド...
データ企業(市場シェア第1位、DAMO Dataが中国国内のデータベース管理システム市場をリード)
最大の市場シェアを誇るDAMO Dataは、中国国内のデータベース管理システム市場をリードしています...